
酒やめて幸せになるかどうかはわからないけど、人生、快適になるのは間違いないです。
酒やめて1496日。飲酒時代の私の人生のテーマは、イベントフルな人生といったところでした。毎日、新しい何かが起きて、という感じですかね。今でいうところのパリピ指向なのでしょう。いつもワクワクドキドキして生きていきたいという思いが非常に強くあったのです。

酒やめて1496日。飲酒時代の私の人生のテーマは、イベントフルな人生といったところでした。毎日、新しい何かが起きて、という感じですかね。今でいうところのパリピ指向なのでしょう。いつもワクワクドキドキして生きていきたいという思いが非常に強くあったのです。

酒やめて1494日。ちょっと前にTwitterで、「落下星」という糖尿病闘病記に関する記事が紹介されていました。で、今現在、リツイートが9千にも及ぶ勢いで、この手の記事、そしてTwitterの利用層が若年層中心だとすると、かなりの反響と考えていいのではないでしょうか。
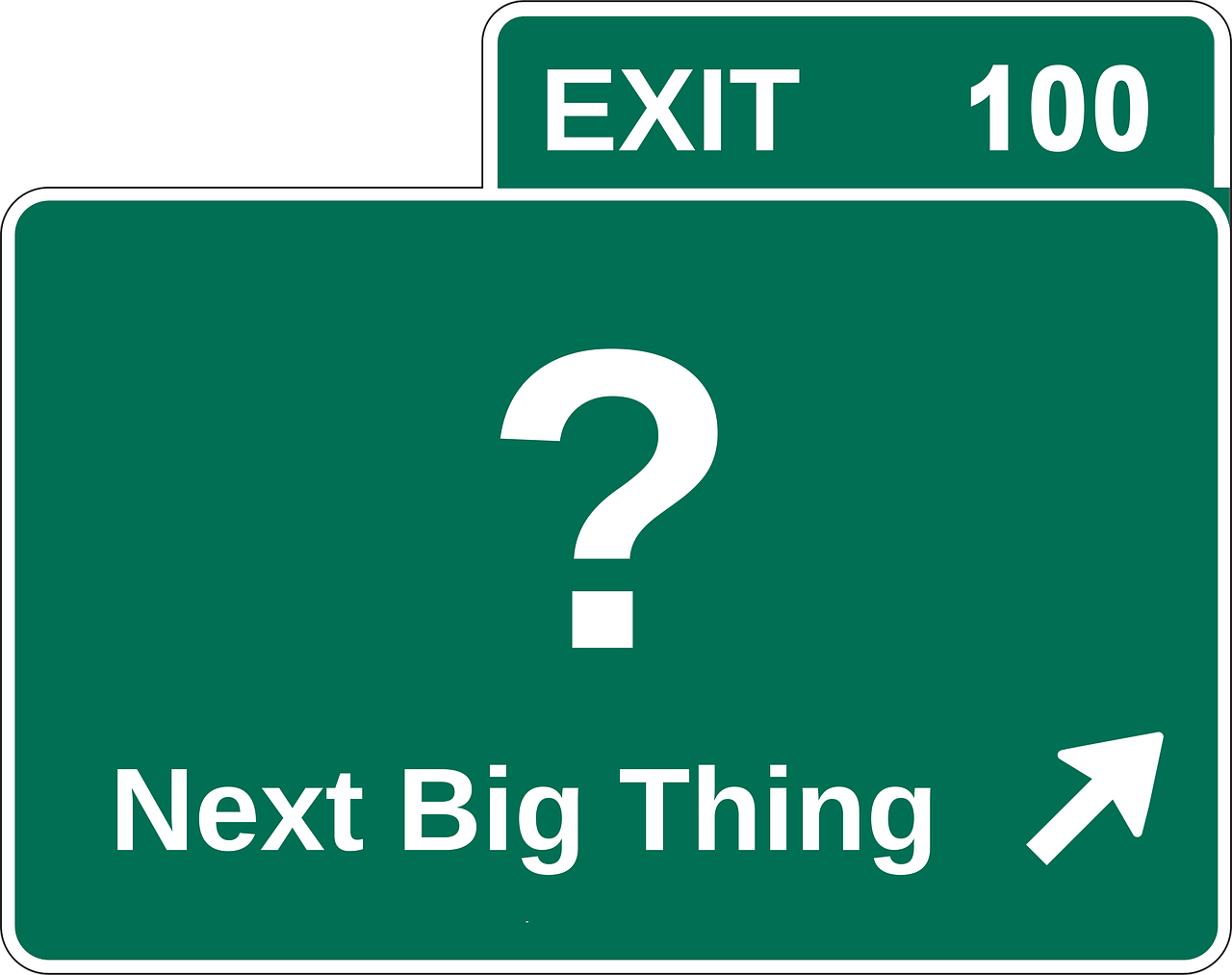
酒やめて1492日。このブログでもさんざん書いてきましたし、断酒した方も一様におっしゃっていますが、酒をやめると甘い物に対する欲求が非常に高まります。いわゆる富井副部長状態ですね。私の場合はとくに低血糖に対する本能的な恐怖があるので、酒をやめて4年以上経つというのに、未だに甘味&白米要求が収まることはありません
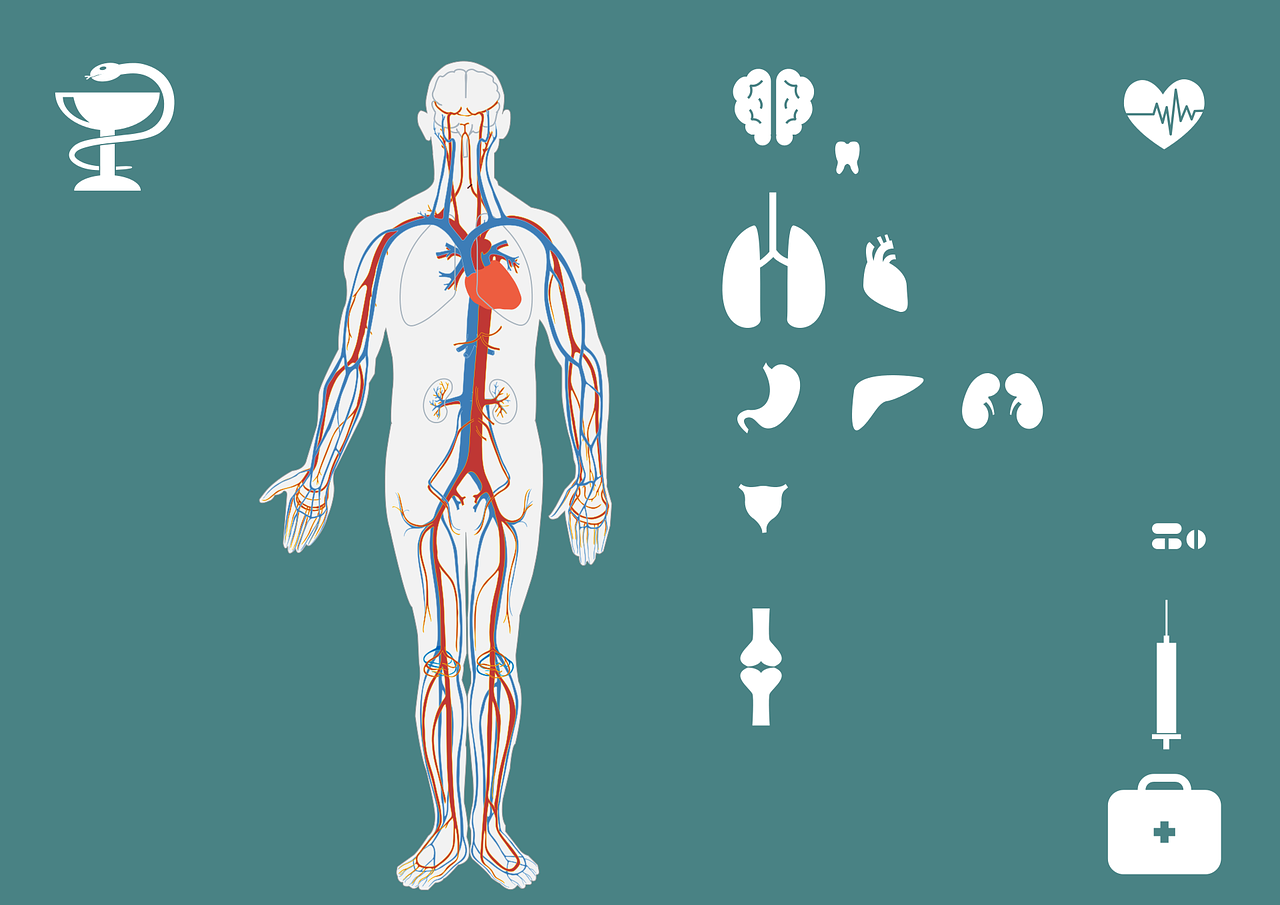
酒やめて1490日。このブログでもしつこいほど書いてきましたが(すみません汗)、酒をやめてから4年ちょっと、身体のほとんどの数値は正常になっています。4年と書きましたけれども、これは半年くらいで正常値になりました。私のようなジジイでも、です。若い人なら2ヶ月ほどでオッケーではないでしょうか。

酒やめて1488日。総務省会食問題の渦中の人だった山田真貴子内閣広報官が、昨日、辞任しました。野党としては、してやったりなんでしょうね。ただ立憲民主党の辻元清美の“追い込み方”は「更迭の決断を!」→「優秀な官僚が潰された!」といったギャグみたいなものでした。

酒やめて1486日。「卒婚」というテーマに興味があり、読んでいるブログがあります。「卒婚・新しい夫婦のかたち」です。なんでも本職のライターの方がやっているようで、文章に品があるので、重いテーマ(?)ながら心地よく読めてしまうのですね。そしてブログ主さんは、夫さんとの関係について模索する意味でブログを書かれています。

酒やめて1484日。今日は、断酒ブログの分際(?)で、ちょっと大それたことを書いてみたいと思います。脳科学者の中野信子さんが、人間が不安や悲観、あるいは嫉妬など、いわゆる負の感情を持つのは、それが人類の歴史において生存のために有利だったから、といったことをおっしゃっています。

酒やめて1482日。最近、というか数年前からSNSなどで忙しさ自慢をする人が増えているといいます。そしてこれは、アメリカのパワーエリートなどに顕著に見られる傾向だそうです。忙しいほどステイタスというわけです。自分の価値が社会で認められている証拠でもあるのでしょう。しかしなんかムカつきますねー。

酒やめて1480日。先日、知人からアマゾンプライムやめたいんだけどどうしたらいいのというメールがありました。確かにアマゾンプライムは、なかなかやめられないという印象があります。一時は、アマゾン組を抜けるにはエンコ詰めしなければいけないなんて冗談もあったくらいで。

酒やめて1478日。一昨日、コロナ禍にしてコロナ下においては飲食店での長時間滞在が社会的にご法度なので、自然、長尻になりがちな飲酒をする人が少なくなっている、家族外出においてはとくに、という話を書かせていただきました。