
人生の後半は「酒とともに」はなかなか難しいよね、という話。
酒やめて1556日。「笑い上戸」「泣き上戸」などという言葉があるように、人間は酒を飲むと感情の振り幅が大きくなります。そしてこのブログでも度々触れていますが、それは酒を飲んでいる時だけでなく、普段の生活にも顕われます。個人的経験ですが、周りを見回してもそうだとは思います。

酒やめて1556日。「笑い上戸」「泣き上戸」などという言葉があるように、人間は酒を飲むと感情の振り幅が大きくなります。そしてこのブログでも度々触れていますが、それは酒を飲んでいる時だけでなく、普段の生活にも顕われます。個人的経験ですが、周りを見回してもそうだとは思います。

酒やめて1554日。ちょっと前に、3回目の緊急事態宣言に伴う飲食店での酒類提供禁止による路上飲みの普及ということについて書かせていただきました。警察への通報や自粛警察と呼ばれる老害も出現し、世の中は完全に酒ディストピアと化しているようですね。

酒やめて1552日。いやあー連休終わってしまいますね。しかしこの連休、私としては大いなる成果がありました。連休中にやってしまおうと思っていた仕事が、なんと4日中に終わってしまったのですね。おかげで本日は、閉鎖されていない駐車場を探して海に行くことができました。

酒やめて、1550日。現在、老後のロールモデル本というものがプチブームのようです。そりゃそうですよね。年金不全+「年金のほかに2千万円貯めろ」+70歳までの雇用確保+副業解禁という4点セットで、老後は自分で何とかしなさいがデフォの世の中になることが明らかですから。

酒やめて1548日。三度目の緊急事態宣言で、なんと酒類の提供禁止という、思い切ったというか飲酒者からすればとんでもないことなのでしょうけれども、そうした施策が講じられました。これを称して「酒ディストピア」とする向きもあるようです。
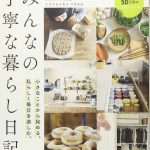
酒やめて1546日。「丁寧な暮らし」という言葉というか概念があります。私は最近、Twitterで初めて知りましたが、もう何年も前から話題になっているようです。そして今では、若干の揶揄とともに語られるケースも多いようです。

酒やめて1544日。酒やめて、基本的にはまったくの健康体になったのですが、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)値だけが高止まり……というか異常値といっていい値を示し病院に行っているということは、このブログでも何度も書いていて恐縮です。

酒やめて1542日。いやーそれにつけてもの朝日です。ネトウヨ用語でいうところのアカピーというやつですね。今週もやってくれました。傘下の週刊朝日が同じく傘下のAERAと連携して「ワクチン敗戦」を声高にまくし立てています。いやまあ、それは事実としてはそうでしょうよ。

酒やめて1540日。そういえばプロ野球が始まっているのですね。MLBも始まっています。去年はコロナで影が薄かったけれども、今年は普通にやっています。とはいえ、MLBのほうは感染者が出て中止になる試合もあるようですけれども。

酒やめて1538日。今、学校現場などでは、すきま時間の活用ということが非常に重要視されています。この背景には、IT教材など短時間でも取り組める教材の普及があります。こうしたものを利用して、とくに忙しい部活生などは移動時間などのちょっとした時間に勉強し、部活との両立を図ろうというわけです。