
できれば若いうちに酒やめて、脳を飼い馴らしておくと後々効いてくるという話【今からでも間に合う人がマジうらやましい】
酒やめて1908日。私事で恐縮ですが、てか個人ブログなので全部私事なのですけど、私はフリーランスという立場で仕事しています。コロナ前までは事務所を借りていましたが、今は自宅での仕事です。一人仕事です。そういうやり方を数十年間続けてきたわけです。

酒やめて1908日。私事で恐縮ですが、てか個人ブログなので全部私事なのですけど、私はフリーランスという立場で仕事しています。コロナ前までは事務所を借りていましたが、今は自宅での仕事です。一人仕事です。そういうやり方を数十年間続けてきたわけです。
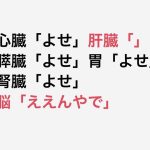
酒やめて1906日。ネット上でこのようなものを見つけてしまいました。有名なのかもしれないですが、私は初見です。いやいやいや怖いです。言うまでもありませんが、酒を飲むとき、身体の各部分がどのような反応するか擬人化したものですね。
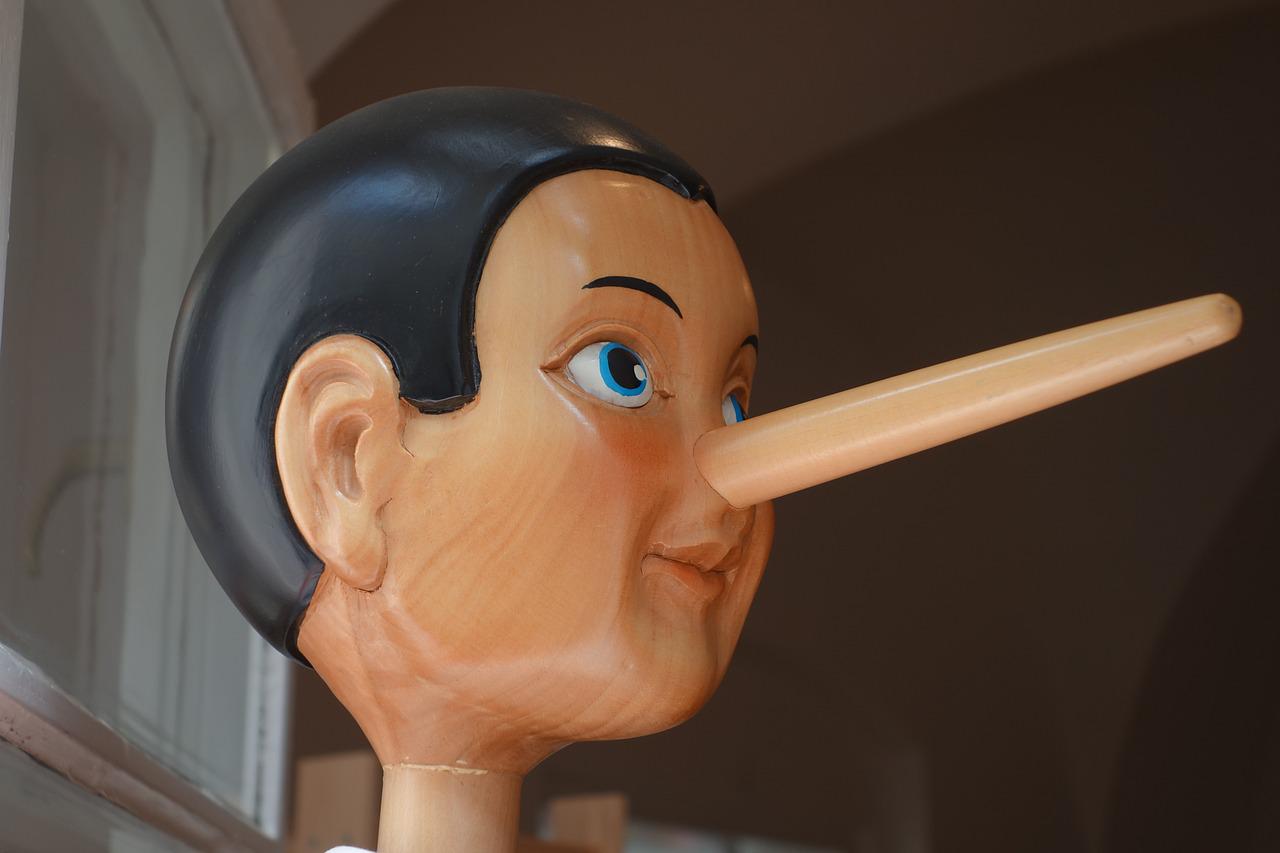
酒やめて1904日。開幕から不調のようだった大谷翔平選手ですが、さすがにここにきて本領発揮しています。そうすると必ず出てくるのがあの議論です。大谷がすごいからってお前がすごいんじゃないからねー、というやつですねー。

酒やめて1902日。思えば私が高校生の頃、教師の言うことは決まっていました。いわく、大学に入ればいくらでも遊べるのだから今は勉強だけしろ! 大学生活というご褒美があって、それを得るために勉強という努力があるという構造ですよね。

酒やめて1900日。ネットが遅いとストレスが溜まります。普通の人はどうするかというと、その原因を調べて改善策を講じるわけですよね、当然ながら。そして契約会社を代えるなら、通信速度や料金のこと、あるいは契約方法によるキャッシュバックの有無なども調べます。
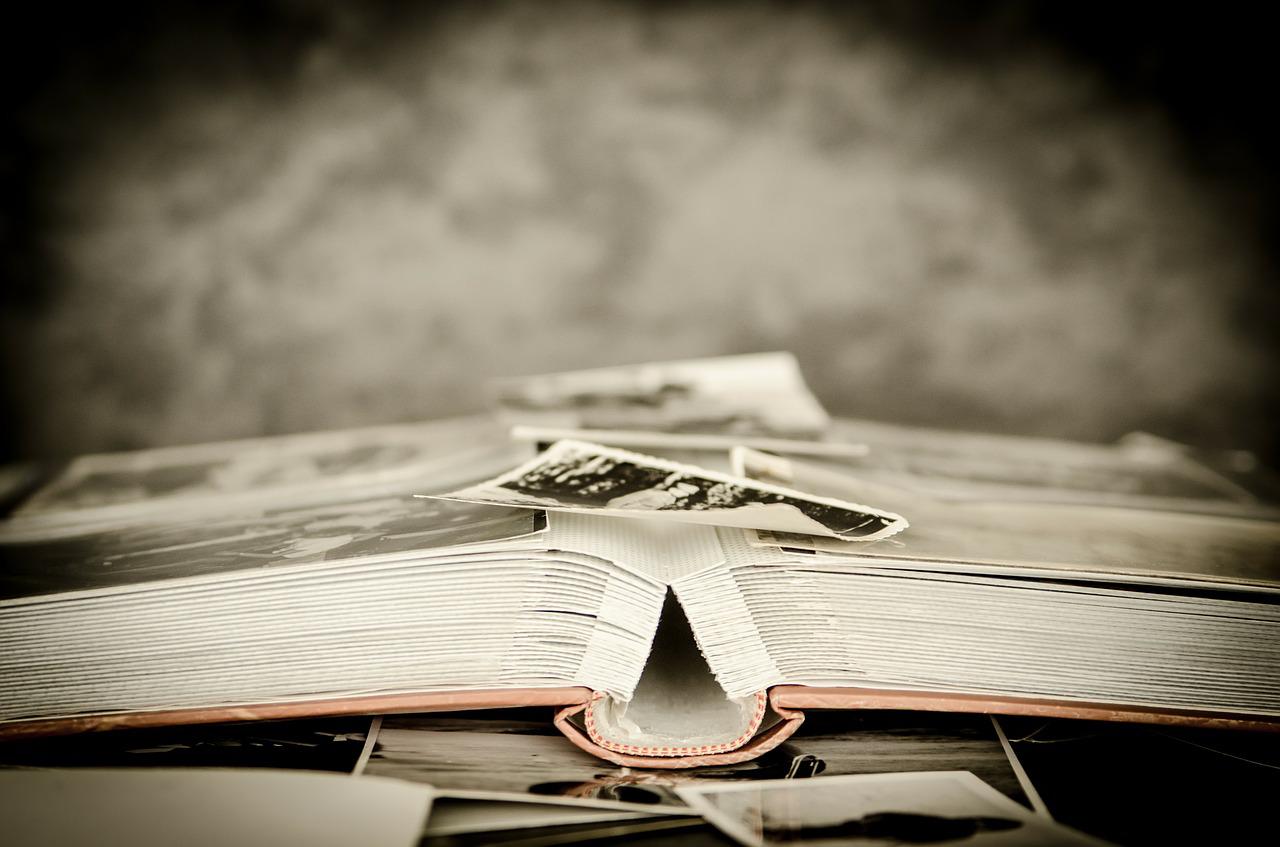
酒やめて1898日。先日、今年86歳になる父と話していて――そのとき父は飲んでいたのですが、そういやおじいちゃん(父の父・当然故人)て、酒飲んでたっけという話題になりました。父が言うには「あんまり飲んでなかったなあ」と。

酒やめて1896日。私が酒やめたとき、当初は「時限」のつもりでした。医者からも1年ぐらいは飲まないようにと言われていましたし、当然そのときは「んな馬鹿な!」だったけれども、ただ、一生飲めないとは思わなかったのです。

酒やめて1894日。ヒッキー――それが物理的なものであれ精神的なものであれ、そのような主人公が新しい一歩を踏み出すといったテーマのコンテンツがあって、コロナの前まではちょっとしたブームだったような気もします。
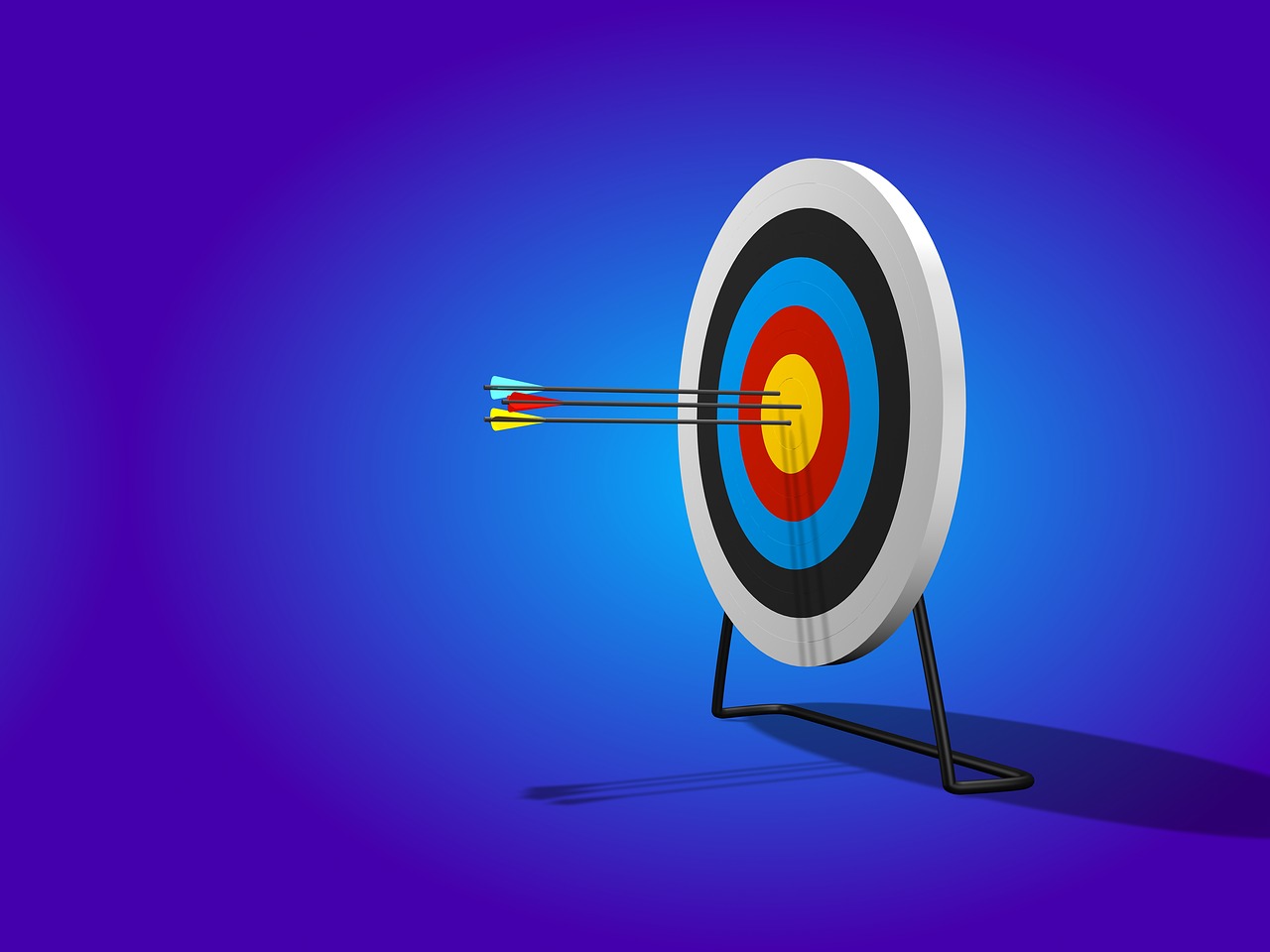
酒やめて1892日。この稿は、断酒者としての、というよりも個人的な妄想の類なのかもしれません。ただしこの時期にどうしても書いておきたいことなので勝手に書かせていただきます。まあ個人ブログなので(汗)。
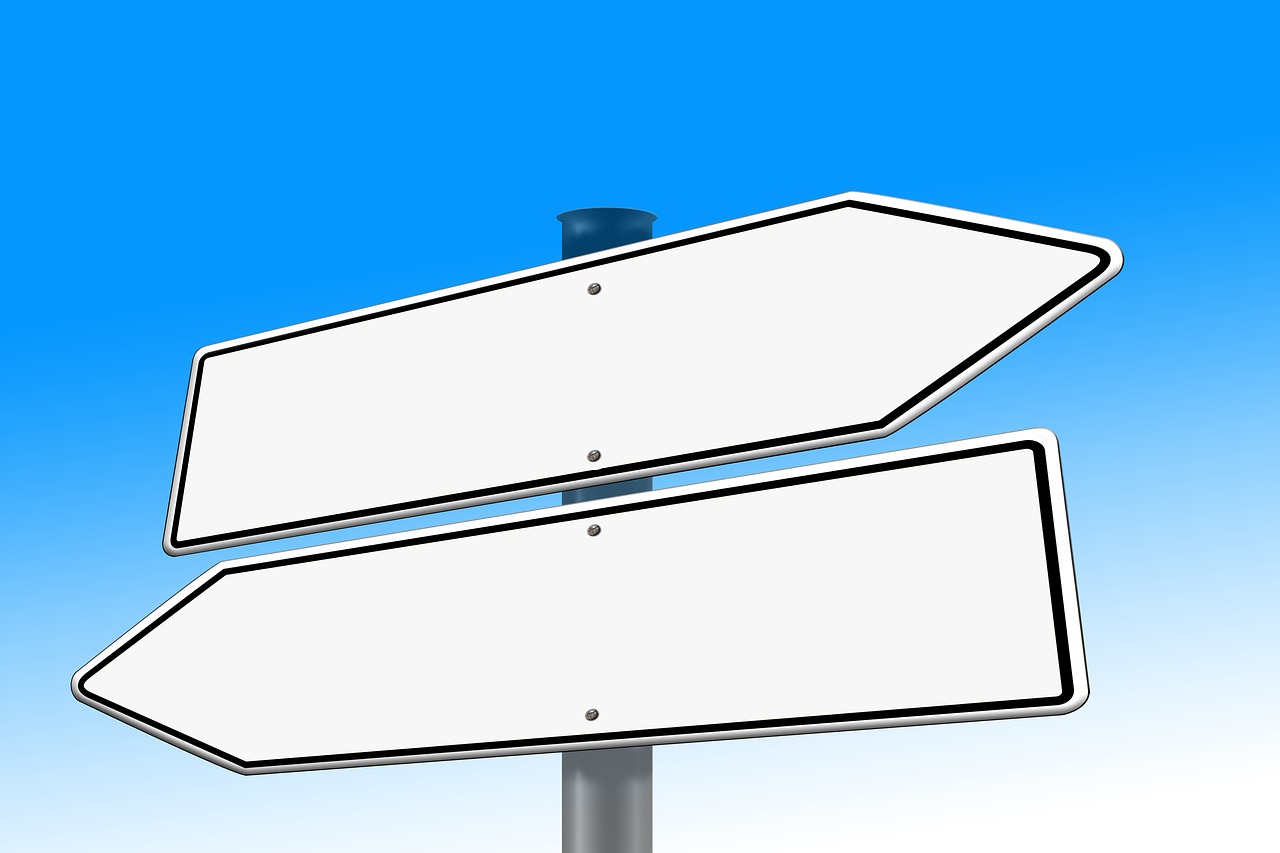
酒やめて1890日。ウィル・スミスの平手打ち事件が、いまだにネット上では話題になっていて、いろんな人がいろんなことを言っています。なぜ単なる平手打ち事件が「いろんな」になるかというと、やはり人々の意識や社会構造の変化が問題を複雑化(?)させているからだと思われます。