酒やめて、2923日
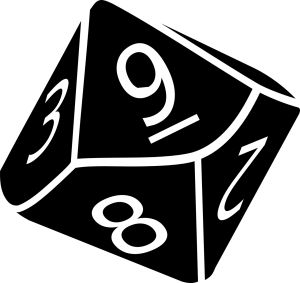
9年前と今とでは状況が大きく変わってしまった!
今日、2月4日で酒やめて9年を迎えます。昨日でまるまる8年経ったわけです。
一応、記念日(?)ということで感慨深げなことを書かせていただくと、酒やめて得たものといえば、「時間」と「経済力」と「エネルギー(気力)」になります。飲んでいた時代は、こういうものが徹底的になかったのですね。
私が断酒した直接的なきっかけはアルコール性低血糖で倒れたことですが、ただし、このまま酒飲んでいたら人生積むなという不安は常にありました。そしてこのような思い、すなわち「酒飲んでる場合じゃない」が、今でも断酒を継続する大きなモチベーションになっています。
ただし私が酒をやめた9年前はまだコロナが日本を襲う前でしたし、日本は失われた30年と言われながらも、円高の後押しを受けて物価も超絶安かったので、酒やめなきゃいかんといった危機感は、その時点では私個人、あるいは私に似たような境遇の人だけだったと思います。
ところが、今は違いますよね。先ごろ亡くなられたモリタク先生が以前から警鐘を鳴らしていた「輸出するものなき円安」に陥り、それに伴い物価も爆上がりしています。その一方で賃金は、先進国の中で最低レベルです。
賃金が上がらないという状況は、私が酒をやめた当時もそうでしたけれども(私の場合はギャラですが)、ただしそのときは円のチート力でなんとか暮らせていた。なので、年金生活の高齢者や公務員はこのままでええやんであり、それを選挙に反映させ、経済が拡大しないという構造もあったと思います。ところがそんな思惑を離れて今は弱い円になり、なおかつ、増税、社会保障費増でもある、と。かなりエグい状況ではあります。
「酒飲んでいる場合じゃない」層が拡大している!?
とまあ、そんなことはお前に言われなくてもわかっとるわいっという向きもあるでしょうが、要するにもう賃金だけでは生活できない、生活はできても将来の展望が拓けない層がどんどん拡大しているわけですよね。すなわち「酒飲んでいる場合じゃない」という状況を多くの人が共有せざるを得なくなっている。政府も副業しなさい、投資しなさいと言っていますし、それはそうした状況が多くの国民に降りかかっている証左でもあるでしょう。
今、通勤手当に対する課税が検討されているようですが、これなんぞは、いわば経費に対する課税であり、税というもの根本を揺るがす暴挙(?)のように思えます。一方、たとえばiDeCoは貯金を控除対象にできるチート技です。この二つを並べてみると、労働よりも投資やで~と政府が言っているようにも感じます。
とにかく、仕事(本業)をしてさえすれば後は酒飲もうがどうしようが自由だという人はどんどんシュリンクしている。であるから、何かをやるための時間とエネルギーを確保し、さらにたとえば投資のタネ銭となる経済力を確保するということは、もうほとんどすべての人に課せられたミッション(?)なのではないでしょうか。
ここで冒頭に戻るのですが、この三つを提供、あるいは復活させてくれるものは、酒やめること……というと語弊がありますが、その有力な方法であることは確かでしょう。とくにそれまで酒とともに人生があった人にとっては一番簡単な方法であり、私の場合それでアドバンテージを得ているかというと微妙なところで悲しいのですけれども、それは私が年齢的にジジイだからであって、多くの人にとってそれは確実にアドバンテージになる。断酒と社会状況のフェイズが合ってきているということを、断酒9年目を迎えるにあたって主張したいのでございました。
カテゴリ別インデックスページはこちらです。